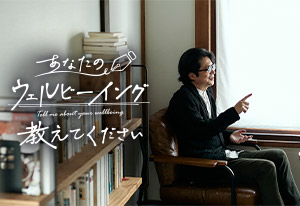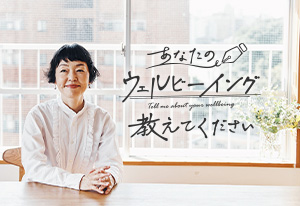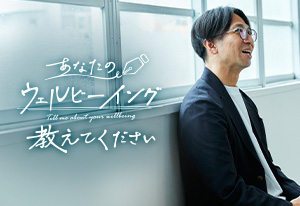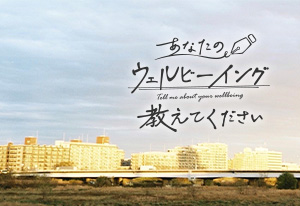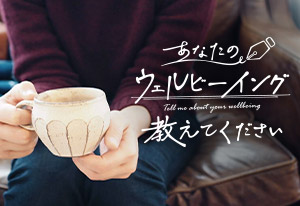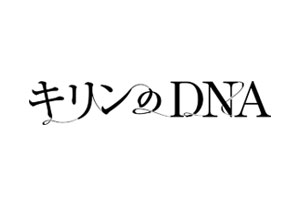さまざまな方に“いい時間”について伺いながら、「心地よい暮らし」や「理想の生き方」を教えていただき、こころとからだの健やかさのために、私たちキリンができることを考えていく「#あなたの“ウェルビーイング”教えてください」。
今回お話を聞いたのは、2025年4月より金沢21世紀美術館の館長を務める鷲田めるろさんです。幼少期からアートに触れ、美術館の学芸員・館長としてアートと人々をつなげてきた鷲田さんの考えるアートとウェルビーイングとの関係とは?
「アートには、知らないものに気付かせてくれる側面がある」と語る鷲田さん。アートや芸術がもたらすもの、そして美術館があり続ける意味について、語っていただきました。
金沢21世紀美術館館長。1973年京都市生まれ。東京大学大学院修士(文学)修了。金沢21世紀美術館キュレーター(1999-2018年)を経て、十和田市現代美術館館長へ(2020-2025年)。2025年4月より現職。第57回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館キュレーター(2017年)。あいちトリエンナーレ2019 キュレーター。東京藝術大学国際芸術創造研究科准教授(2023年~)。
01
見えているつもりで何も見えていなかったんだという喜び
私にとってアートは、長らくいろいろな付き合い方をしてきた存在です。幼少期に父の仕事の都合でしばらくヨーロッパにいたことがあり、そのころは父によく美術館へ連れて行ってもらいました。今思えば、かなり偏りがある趣味だったんだなとも感じますが、ゴッホなどの後期印象派、表現主義*の美術をよく見せてもらった記憶があります。その影響を受けていたので、日本の学校に戻ったあとも「自由に描くことがアートだ」という感覚で絵を描いていました。
*20世紀初頭のヨーロッパ、とくにドイツを中心に広がった芸術運動。客観的な現実の再現ではなく、内面の感情や主観を強く表現することを重視した。ゴッホの絵に見られる強烈な筆致や激しい色使いで心情を吐き出すような表現が、その後の表現主義に強い影響を与えた。
転機が訪れたのは高校時代。美術の先生に「よく見て正確に描け」と、徹底的にモデルデッサンをさせられました。西洋人モデルのデッサンをすると、無意識のうちに日本人である自分の顔に近づいていってしまって、先生から「そうじゃない、こうなっているだろう」と指摘される。それまではのびのび描いていたら褒められたのに、自由に描くと怒られる状況になったんです。でも、自分としては、その状況が嫌ではなかった。「見えているつもりで、実は何も見えていなかったんだ」ということに気付かされる。それがすごく快感だったんです。
もうひとつ、先生と自分が対等だと思えたこともうれしかったんですよね。その先生は彫刻家でもあったので、経験も豊富で、きっとすべてが見えているんだと、最初は思っていました。先生は自分よりずっと長い時間「よく見て正確に描く」というトレーニングしてきているわけですから。だけど、やりとりを重ねるうちに、先生にも見えていないことがあるのかもしれないと気付いたんです。先生にしか見えていない部分というのは間違いなくあるのですが、よく見て正確に描くという行為そのものは自分と一緒なんだ、と。
中学生くらいまでの「子どもは子どもらしく、のびのびと好きなことを描きましょう」という状況を、私はメタ的に見て、「子どもらしく」描いていたところがあったのですが、それで評価されてうれしい一方で、どこか物足りなさも感じていた。高校生になり、その先生と向き合えたことで、対等なアーティストとして扱われたような気がしたんです。そこから美術がより好きになりました。
02
世界には知らないことが満ちているという豊かさ
そんな経緯で美術の世界にのめり込んでいったこともあり、自分の中にあるものを表現していくことよりも、「見ることで更新されること」に強く惹かれるようになりました。美術作品と向き合い、世界はまだまだ知らないことで満ちているという事実に気付く。そこに豊かさがある、と。
今は美術館に関わる立場として、「知らなかったことに気付き、世界が変わって見える」みたいな経験をお客さんに提供できたらいいなと考えています。作品と向き合って得られることもあるだろうし、誰かと感想を送り合うことによって気が付くことや、解説を読んで知ることもあると思います。特に最近の現代アートはさまざまな政治性、地域性、社会性を孕んでいますから、作品を通してさまざまなことに触れられます。今まで知らなかったことを知る、見えていなかったことを見るというのは、単に知識欲を満たすという意味ではなく、「知るということは難しいことなんだ」、「自分が知っていることは限られた世界のことなんだ」と感じることそのものに豊かさがあるのだと思っています。
きっと人によっては、本を読んだり、演劇を鑑賞したり、音楽を聞いたりしても同じような経験は得られるでしょう。ただ、私にとっては、そういう経験をくれる存在が美術だった。私自身、比較的幸せに生きてきたほうだと思うのですが、それでも美術と出会えていなかったらまた違う人生になっていただろうし、違う人間になっていただろうと想像できます。そして、美術のない人生は嫌だなともやっぱり思うんです。
03
新しさを取り入れることで変化していく街のなかで
金沢21世紀美術館は2004年に開館したので、昨年20周年を迎えました。この20年でアートや美術の捉え方や楽しみ方に何か変化があったということはあまり感じませんが、現代美術に対するイメージは大きく変わったのではないでしょうか。
開館した当時は、現代美術といえば「難しいもの」というイメージが強く、「知識がないとわからない」、「近寄りがたい」と思われる存在でした。『スイミング・プール』(レアンドロ・エルリッヒ)に象徴されるように、作品の中に入り込み、驚きや楽しさを直感的に体験できる。頭で理解しなくても自然とアートと関われる。そういった作品が、来館者の現代美術に対する視野を大きく広げたのだと思います。
金沢という街は、もともと伝統工芸が残る文化的な街です。その街に新しい美術館を作るとなると、順当に考えれば伝統工芸にフォーカスを当てた美術館になっていたと思うのですが、ここではあえて新しい芸術を取り入れるという挑戦をしました。伝統工芸の作り手たちにとっては、最初こそ驚きがあったかもしれませんが、時代ごとに新しいものを取り入れ、挑戦を続けてきた自分たちの営みと重ね合わせながら、美術館の新しい挑戦を受け入れてくださったのだと思います。
この場ができたことで、それまでなかった作家同士の交流も生まれています。伝統だけでなく、新しさを取り入れることで文化都市としての金沢が形づくられてきた、そうした流れの中にこの美術館もあると感じています。
04
「変わらずものを残し続ける」という美術館の役割
私は、2020年から2025年まで、この金沢21世紀美術館を離れ、青森県十和田市の「十和田市現代美術館」で館長をしていました。ちょうどコロナ禍の頃でした。さまざまなことが不要不急とされ休止に追いやられた時期でしたが、我々も多分に漏れず閉館していた期間があります。県外の人が訪れる目的となる美術館は、感染者のいない街にリスクをもたらしかねない存在ということで閉館は避けては通れない選択でした。
世の中の状況が落ち着き、再開のタイミングで考えたのが、「美術館の本当の役割とは何か?」ということでした。美術館で作品を見て心が豊かになるという側面はたしかにありますが、それだけでは再開する理由としては不十分だと感じたんです。
ちょうど閉館を決断したタイミングは、ある企画展の開会直前でした。そこに出展予定だった作家とのやりとりのなかで、「美術館は100年閉まっていてもいい。100年後まで作品を残していてくれれば」と語る人がいて。その言葉に、美術館が「変わらずものを残し続ける場所」であることの意味を強く実感しました。
その後、2025年春に金沢21世紀美術館に戻り、館長になりました。伝統的なものに対して、最新を取り入れていくところからはじまったこの美術館も開館から20年。20年も経つと最新は更新されていくわけですから、同時代の美術を見せる美術館という当初のコンセプトを守るためには、やはり常に新しい試みを積極的に取り入れていく必要があると感じています。2027年に施設の大規模改修を予定していますが、これからも新しい試みを積極的に取り入れ、若いキュレーターたちが実験的な企画に挑戦できる場にしていきたい。今後はダンスや演劇、音楽といったパフォーミングアーツなどの美術と隣接する領域にも力を入れていきたいと構想を膨らませています。
05
時間を経てもアート作品は変わらない。変わるのは人
ウェルビーイングにアートができることはなんだろうと考えたときに、やはり自分がアートに惹かれた理由でもある「知らないものに気付かせてくれる」ことなのではないかと思います。美しい絵を見て心が豊かになるという精神面の話ではなく、作品と出会って、訳が分からなくなって、だけど見ているうちに、自分はものがちゃんと見えていないんだと気付かされ、考える。その視点を持つことで、また人とつながれる。そういう側面もあるのではないか、と。
さらに人と話をすることで、自分が見えてないところに気付くこともあると思いますよね。自分が気づくこともあるし、自分が誰かに気付きを与えることもある。お互い様なんですよね。そういう感覚が社会的な豊かさにつながっていくのではないでしょうか。
金沢21世紀美術館は、ガラス張りで通り抜けもできる公園のような美術館なので、小さなお子さんから、近所のご老人まで老若男女たくさんの方が訪れてくれます。たとえば、18歳の人がある作品を見て感動したとして、それを20年後、38歳になったときに再び見たら、違う印象を受けるということもあると思うんです。「あのとき見た作品、こんなだったんだ」と。作品自体は変わらないので、変わるのは見る側。それまでの時間のなかでの経験などによって、見えなかったものが見えてくるということもあるので、時間をおいて作品と出会い直すというのもぜひ、やってもらいたいですね。
そのためにも美術館は作品を保存し続け、あり続ける必要があると感じています。たとえ実際に訪れなくても、作品がそこにあることで、また見に行く可能性が自分の中に生まれる。そうした「訪れる可能性」が心の支えになることもあると思うので。
この記事をシェアする
お酒に関する情報の20歳未満の方への
転送および共有はご遠慮ください。