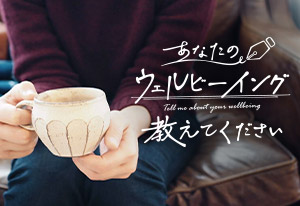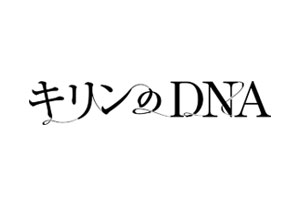病気、未病、健康。どんな人にも必要な「おいしさと栄養」

佐藤今日はよろしくお願いいたします。私は2010年にキリンに入社して、飲料に限らず、新しい事業につながるような研究開発に携わってきました。2019年にエレキソルトの事業提案をしたところ、それが社内のコンテストを通過して、2020年からエレキソルトの事業化に向けて取り組んでいます。
もともとは減塩療法をしている方に食事をより楽しんでいただくために開発したエレキソルトですが、ふだんの食事の楽しさを広げるツールとしても可能性を模索している最中なんです。長谷川さんのやさしく楽しいレシピをSNSでいつも楽しみにしているので、今日はお話を伺えるのが楽しみです。
長谷川さんが料理研究家になった経緯はどんなものだったのでしょうか?
長谷川私はもともと料理が好きだったこともあって、管理栄養士の資格が取れる大学に進んだのですが、いろいろな授業を受ける中で一番興味深いと感じたのが栄養学だったんです。ただ、病態に対して明確なアプローチがある栄養学よりも、健康な人たちの病気を予防することや、健康をより増進していくことに関心がありました。
佐藤はじめから料理研究家を目指していたわけではなかったんですね。
長谷川そうなんです。実は子役として活動していた時期もあったので、微々たるものかもしれませんがそういう影響力がある状態で食について発信していくことそのものが公衆栄養学※につながるんじゃないかという思いもありました。そこで、自分がやりたいことに近い職業って何だろう?と考えたときに浮かんだのが料理研究家だったんです。
※公衆栄養学…地域の方々の健康づくりを栄養・食生活から支援するための必要な知識を学ぶ科目
栄養のことを発信するとなると、どうしてもカタくなるイメージが私のなかにあって(笑)。正しい栄養の知識も、わかりやすく楽しいものでないと、届くべき若い層にはなかなか届かない。とはいえ、キャッチーさを追求すると「これを食べたらニキビがなくなる」みたいな、ちょっと極端な情報になってしまったりする。私はレシピという身近な媒体を使って「これ、おいしいから食べてみて」って紹介していくことで、自然と身体の栄養状態も良くなったらいいなと考えています。
佐藤たしかに長谷川さんのレシピは、「おいしそう」「やってみたい」と思えるものが多いんですよね。本当にシンプルなレシピだから実際に取り入れやすくて。私自身とても面倒くさがりなので、長谷川さんのように気軽に暮らしを楽しめるヒントを発信していただけるのは大変ありがたいです。

左:エレキソルト スプーン(実験機)、右:エレキソルト 椀(実験機)。※販売機とは形状が異なります。
エレキソルト事業も最初は「病気で減塩が必要な方に食事をより楽しんでもらうために」というところからスタートしたのですが、未病・予防くらいの段階で意識していく必要があると考え直して、途中から事業の方針を変えたんです。病気のため、健康のため、と指導的になっていくとやっぱりうんざりしてしまう。それよりも、食の楽しさや面白さを伝えていくほうが重要なのかなと思います。そういう意味でも、長谷川さんのレシピや伝え方は参考にさせていただいていました。
長谷川ありがとうございます、嬉しいです。私自身もそうなのですが、健康な人に「減塩しましょう」って言っても、なかなか実践できないんですよね。だから栄養学にあまり興味がない人でも楽しめるような発信をすることは、普段から意識しているかもしれません。