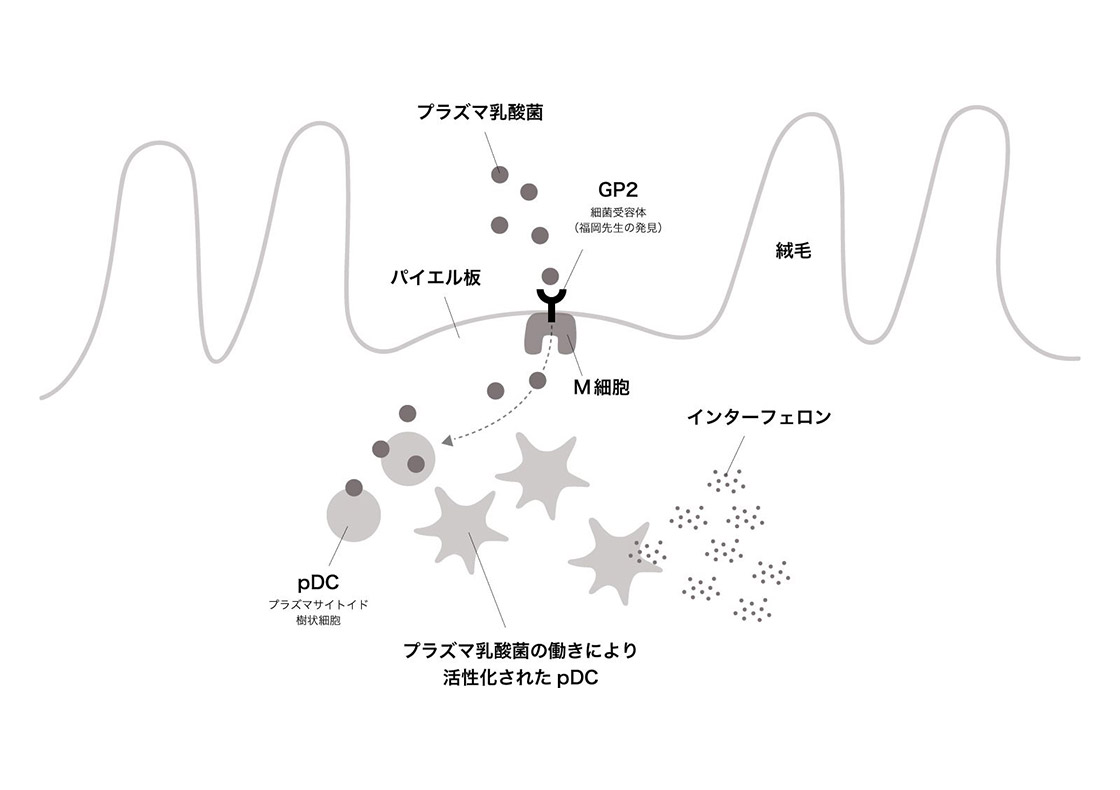「生命は、もっと合理的なものだと思っていた」
お二人は初対面ということですが、もともと藤原さんは福岡先生のファンだったそうですね。
藤原はい。対談にあたり、あらためて福岡先生の『生物と無生物のあいだ』を読み返しました。私はここまで見事に科学を文学的、哲学的に表現した本をほかに知りません。科学ってどうしても内側に閉じがちな学問ですが、この本はサイエンスの現場のことが一般の人にも伝わる内容になっている。どうして、こういうアプローチで本を書こうと思われたのですか?

藤原大介
福岡誰かに向けて書いたというより、あるとき、自分の考えていることを自分で整理してみようと思い立ったのがきっかけですね。20年ほど前に、これまでやってきた研究にある種の反省というか挫折のような気持ちを味わって、大きくアプローチを変えてみようと考えたタイミングで書いたのが『生物と無生物のあいだ』でした。

福岡伸一氏
藤原その挫折とは、どういうものだったのでしょうか?
福岡私はもともと虫が好きな子どもで、ドリトル先生シリーズや『ファーブル昆虫記』を読むことで生物全般に興味を持ちました。以来、生命の不思議を探索したいという気持ちが芽生えたんです。ところが、大学で学ぶ生物学はどうしても細胞分子や遺伝子といったミクロな世界に入ってしまう。特に、私が大学生だった1980年代はPCR(「Polymerase Chain Reaction」の略。ウイルスなどの遺伝子を増幅させて検出する技術)をはじめさまざまなツールが使えるようになる分子生物学の夜明けのような時代でもあり、生命を切り分けてさらにミクロのほうへと進んでいきました。それはそれでいろんな発見もあったのですが……。
藤原「生命の不思議を探索したい」という根源の欲求は満たされなかったと。
福岡はい。細かいことをいくら追求しても「生命全体のことは何もわからない」ことに気づいたんです。それを知るには、もっと大きな視点で生命をとらえなくてはいけないと考えました。
藤原それで、「生物とは何か」について真っ向から考察する『生物と無生物のあいだ』を書かれたと。あらためて、あの本は生物現象の本質に触れられていると感じました。研究室にいるとグラフで物事を判断しますよね。上がったとか下がったとか、統計的な有意差がどうかとか。でも、それって単なる数字であってまったく生命の本質ではない。一方で、福岡先生はそうした研究の奥にある生命の本質の現象のことを見事に描写されています。
福岡ありがとうございます。
藤原なかでも私が感銘を受けたのは「動的平衡」という生命観です。「生命は絶えず率先して分解を行ないつつ、同時につくりなおす動的平衡を繰り返していく」と。私はそれを大学で教わった「プロテイン(タンパク質)がターンオーバーする」という言葉だけで済ませてしまっていましたが、福岡先生の『動的平衡』という本を読んで、自分自身のタンパク質が「いま、この瞬間にも移り変わっている」ということを実感できるようになりました。
福岡おもしろいのは、単に細胞が古くなったからと壊して交換するのではなく、できたてホヤホヤでも壊しているということですよね。壊れたり古くなったりする前にあえて自ら壊してエントロピーをどんどん捨て、つくり変えるというところに生命の躍動があるのではないかと思います。
藤原すごいことですよね。私は生命とは、とても合理的にできているものだと思っていました。でも、まだ腐っていないタンパク質を捨ててしまうなんて、じつは非合理的なんじゃないかと。
福岡短いスパンでみると、なぜそんなに非合理的なことをやっているんだろうと感じますよね。ただ、数十年、数百年、あるいは生命誕生以降の38億年という長いレンジで生命の歴史全体を見渡してみると、あえて先回りして秩序を壊しながらつくり変えるということが、生命が唯一存続する方法だったんじゃないかと思いますね。